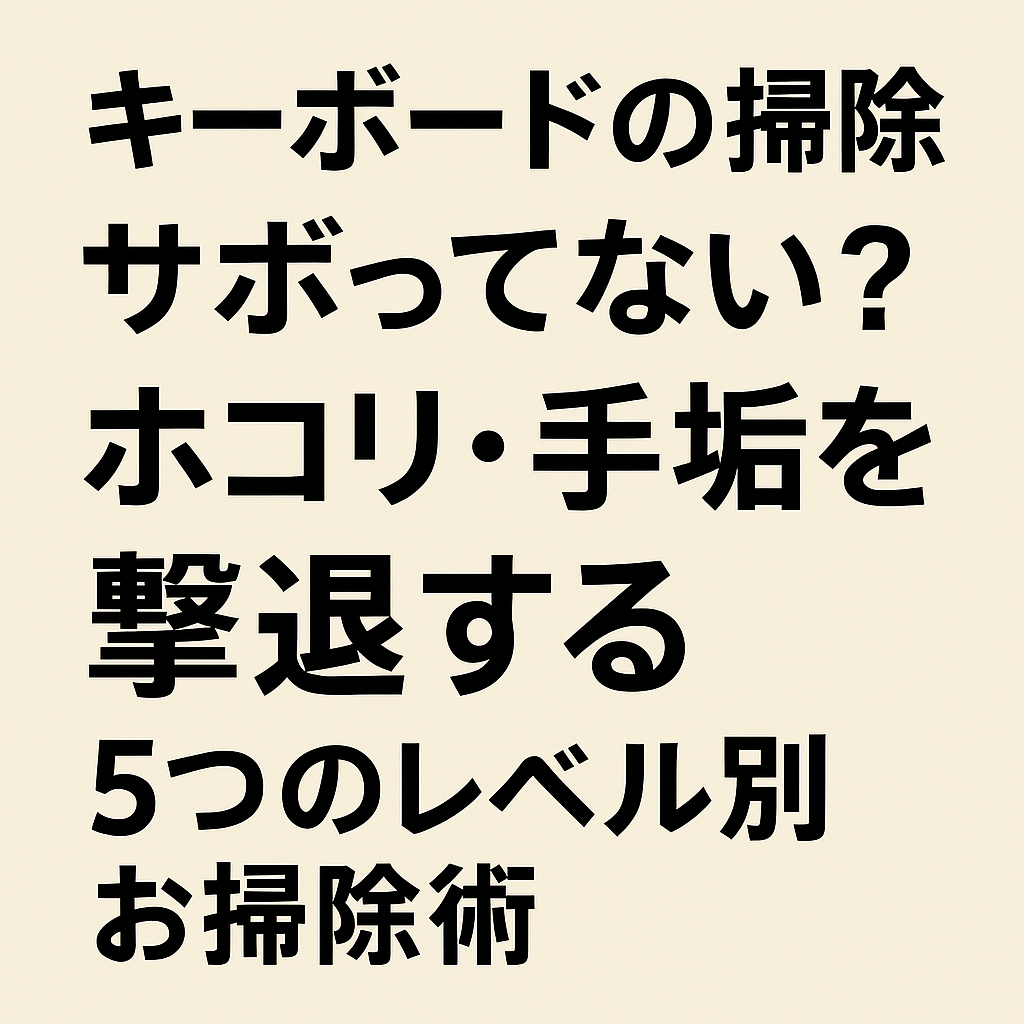出張や旅行で、いつもと違う都市の駅を歩いている時。エスカレーターに乗った瞬間、ふと周りの視線を感じて「あっ…」と焦った経験はありませんか?
そう、エスカレーターの「立ち位置」問題です。
エスカレーター、福岡は左立ち?右立ち?関東と関西の違いと、実は知らない本当のマナー
関東では左側に立ち、関西では右側に立つ…というのは有名な話ですが、「そもそも、なんでそんな違いが生まれたの?」「じゃあ、私たちの住む福岡はどっちが正解なの?」と、その理由や地域のルールまで詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。
そして、実は近年、この「片側を空ける」という慣習そのものが見直されつつある、という事実も。
この記事で、一緒に見ていくこと
- 🤔【結論】福岡はどっち?関東・関西・福岡の立ち位置マップ
- 📜 歴史の謎!関東「左立ち」vs 関西「右立ち」、由来とされる説を解説
- 😅【私の体験談】大阪出張で、私が「右側の壁」になった話
- ⚠️【超重要】実は非推奨?鉄道会社が呼びかける本当のマナーとは
- 📜 ついに条例も登場!「歩行禁止」の最新動向
この記事を読めば、もうどの都市のエスカレーターでも、自信を持ってスマートに振る舞えるようになりますよ。
【結論】福岡は「左立ち」!まずは立ち位置の違いを知ろう
まず、日本国内の主な立ち位置の傾向を見てみましょう。
- 【関東・東日本エリア】
左側に立ち、右側を歩く人のために空けるのが一般的。 - 【関西エリア】
右側に立ち、左側を歩く人のために空けるのが一般的。 - 【そして、福岡は…】
左側に立つのが主流。東京などと同じ関東式です。
九州の他の県や、名古屋なども基本的には「左立ち」ですが、大阪に近い京都や兵庫、奈良などは「右立ち」が主流。実に興味深い文化の違いですね。
歴史の謎!関東「左立ち」vs 関西「右立ち」、なぜ違いが生まれた?
では、なぜこんなにもハッキリと地域差が生まれたのでしょうか。これには、決定的な記録はなく、いくつかの有力な説が存在します。
関東「左立ち」の由来説
侍(さむらい)の作法説:これが最も有名な説です。武士は、左腰に差した刀の鞘(さや)がぶつからないように、また、いざという時に右手で刀を抜きやすいように、道の左側を歩くのが基本でした。この「左側通行」の文化が、エスカレーターの立ち位置にも引き継がれた、というものです。
関西「右立ち」の由来説
大阪万博・阪急電鉄説:こちらも非常に有力な説です。1970年の大阪万博の際に、国際的なスタンダード(右側通行の国が多い)に合わせて「右にお立ちください」とアナウンスされたのがきっかけ、というもの。また、それに先駆けて、1967年に阪急電鉄が梅田駅にエスカレーターを設置した際、同じアナウンスをしたことが関西での「右立ち」を定着させたとされています。
😅【私の体験談】大阪出張で、私が「右側の壁」になった話
この地域差、知識としては知っていても、いざその場に行くと、長年の習慣というのは恐ろしいものです。
数年前、大阪へ出張に行った時のこと。普段の癖で、何も考えずにエスカレーターの左側にスッと立ちました。すると、どうでしょう。後ろから来た人たちが、私の右側を通り過ぎるのではなく、私の後ろでどんどん詰まっていくのです。
「あれ、なんか流れが悪いな…?」と不思議に思っていたら、痺れを切らした一人が私の左側を「すみません」と言いながら追い越していきました。その瞬間、ハッと気づいたのです。
「しまった!ここ大阪だった!私が流れを止める“右側の壁”になってる!」
慌てて右側に移動しましたが、時すでに遅し。後ろに並んでいた方々の「(この人、分かってへんなぁ…)」という、無言の視線が背中に突き刺さりました(笑)。頭では分かっていても、体が勝手に動いてしまう。文化の違いを肌で感じた、ちょっぴり恥ずかしい思い出です。
⚠️【超重要】実は「片側空け」は非推奨?本当の正しいマナーとは
さて、ここまで地域差について解説してきましたが、ここで非常に重要な事実をお伝えしなければなりません。
実は、鉄道会社やエスカレーターのメーカー各社は、長年にわたり「片側を歩くために空ける」のではなく、「2列に並んで立ち止まって利用してください」と呼びかけているのです。
なぜ「立ち止まる」のが推奨されるのか?
- ① 安全のため
エスカレーターでの歩行は、バランスを崩して転倒したり、他の利用者と接触したりする原因となり、大変危険です。 - ② 配慮のため
片側を空ける慣習は、体の不自由な方や怪我をしている方、大きな荷物を持っている方などが、片側に寄ることを強いてしまうことになります。誰もが安心して利用できるよう、両側に立ち止まることが推奨されています。 - ③ 輸送効率のため
意外なことに、片側を空けて歩くよりも、2列で立ち止まって乗る方が、より多くの人をスムーズに運べるという調査結果もあります。
「急いでいる人のために空ける」というのも一つの思いやりですが、様々な事情を抱えた人がいることを考えると、「歩かずに2列で乗る」ことこそが、本当の意味での“思いやり”なのかもしれませんね。
ついに条例も登場!「歩行禁止」の最新動向
この「立ち止まり」の動きは、近年さらに加速しています。
- 2021年10月には、埼玉県で全国初となる「エスカレーターでの歩行を禁止する条例」が施行されました。(罰則はありません)
- さらに、2023年10月からは、名古屋市でも同様の条例が施行されています。
これは、「慣習」や「マナー」から一歩進んで、「ルール」として定めようという社会的な動きの表れです。今後、他の自治体でも同様の条例が制定される可能性は十分に考えられます。
まとめ:地域ルールを知りつつ、思いやりの心を持つことが大切
エスカレーターの立ち位置問題、奥が深いですね。最後に、この記事のポイントをまとめます。
【エスカレーター立ち位置 ポイントまとめ】
- 地域差という「慣習」:福岡は「左立ち」。関東と同じ。関西は「右立ち」。
- 由来:侍文化や万博など、歴史的な背景から生まれた諸説がある。
- 公式という「ルール」:鉄道会社などは、安全と配慮の観点から**「2列で立ち止まる」**ことを推奨している。
- 最新動向:埼玉県や名古屋市では**「歩行禁止の条例」**が施行されている。
その場の慣習に合わせることも円滑なコミュニケーションの一つですが、エスカレーターは誰もが利用する公共の設備です。
周りには、様々な事情を抱えた人がいるかもしれない。そのことを心に留め、急いでいる時こそ一歩立ち止まる「心の余裕」を持つことが、一番スマートで、かっこいい乗り方なのかもしれませんね。